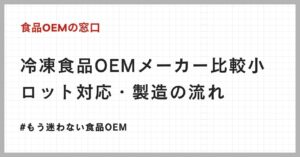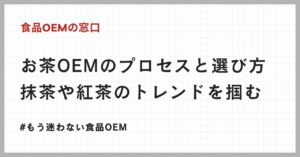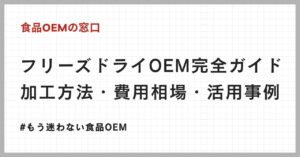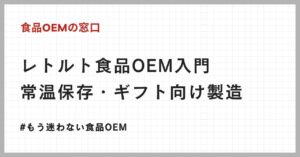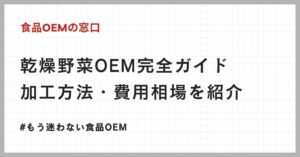食品OEM商品企画で差がつく7つのアイデア出し手法
食品OEMで新商品を企画する際、どうすれば他社と差別化できるアイデアが生まれるのでしょうか?
「いつも同じような企画ばかりになってしまう」「競合と似たような商品になってしまう」と悩んでいませんか?
本記事では、食品OEMの商品企画において、真に差別化できるアイデアを生み出すための7つの手法を紹介します。これらの手法を活用することで、市場で埋もれない、独自性のある商品企画が可能になります。
1. 市場ギャップ分析法:ニーズの隙間を見つける
市場ギャップ分析法とは、既存市場の中で満たされていないニーズを見つけ出す手法です。
まず、ターゲット市場の既存商品をリストアップし、それぞれの特徴や価格帯、ターゲット層を整理します。次に、それらの商品が満たしていないニーズや課題を特定します。

例えば、健康志向の高い30代女性をターゲットにしたプロテイン市場を分析したとします。既存商品の多くは「高タンパク・低カロリー」を謳っていますが、「美味しさ」や「続けやすさ」に課題があることが見えてきました。
このギャップを埋めるために、「毎日続けられる美味しさ」と「手軽さ」を兼ね備えたプロテイン商品を企画。フリーズドライ製法を活用した果物風味のプロテインスナックという新しい形態で市場に参入することで、差別化を図ることが可能です。
市場ギャップ分析で重要なのは、表面的なニーズだけでなく、潜在的なニーズを発見することです。消費者が「こんな商品があればいいのに」と思っていても、まだ言語化されていないニーズこそ、大きなビジネスチャンスになります。
市場ギャップ分析の実践ステップ
- 競合商品の徹底リサーチ(価格帯、原材料、ターゲット層、販売チャネル)
- 消費者レビューの分析(不満点や改善要望に注目)
- SNSでの関連キーワード分析(消費者の本音を探る)
- 小売店バイヤーへのヒアリング(売場で感じる消費者ニーズ)
この手法は特に、成熟市場や競争の激しい分野で新規参入する際に効果的です。
2. クロスインダストリー発想法:異業種からヒントを得る
クロスインダストリー発想法は、全く異なる業界のアイデアや技術を食品分野に応用する手法です。
異業種の成功事例や革新的なアプローチを研究し、食品OEMに取り入れることで、従来にない斬新な商品企画が可能になります。

化粧品業界の「レイヤリング」という概念を食品に応用した例を見てみましょう。化粧品では複数の製品を重ねづけすることで効果を高めますが、この発想を取り入れた「〇〇が乗ったケーキなど重ね食べ」を前提としたデザートが話題になりました。
別の例では、アパレル業界の「カプセルワードローブ」(少ない服で多くのコーディネートを楽しむ考え方)から着想を得た、少量の調味料で様々なアレンジが楽しめる調味料セットが人気を集めています。
異業種からの発想を得るには、意識的に自分の業界以外の情報に触れる習慣が大切です。
クロスインダストリー発想を促進する方法
- 異業界の展示会やセミナーに参加する
- 多様な業界の雑誌や専門書を定期的に読む
- 異業種交流会に積極的に参加する
- 他業界の成功事例を食品に置き換えるワークショップを実施する
この手法は特に、マンネリ化した商品企画に新しい風を吹き込みたい時に効果的です。
3. 逆転発想法:常識を覆すアイデア創出
逆転発想法は、業界の常識や既存の概念を意図的に逆転させることで、革新的なアイデアを生み出す手法です。
「当たり前」とされていることを疑い、あえて反対の発想をすることで、誰も思いつかなかった商品企画が生まれます。

例えば、「健康食品は味が犠牲になる」という常識を覆し、「美味しさを最優先した健康食品」というコンセプトで開発されたグラノーラが大ヒットした事例があります。また、「冷凍食品は保存食」という概念を逆転させ、「冷凍だからこそ実現する究極の美味しさ」を追求した高級冷凍食品ブランドも注目を集めています。
逆転発想を実践するには、まず業界の「当たり前」をリストアップすることから始めましょう。そして、それぞれの「当たり前」に対して「もし逆だったら?」と問いかけてみるのです。
逆転発想法の実践例
- 「食品は消費期限が短い」→「100年保存できる非常食」
- 「調味料は料理に使うもの」→「そのまま食べる調味料菓子」
- 「ドレッシングは液体」→「粉末状のふりかけドレッシング」
- 「お菓子は甘いもの」→「メインディッシュになる塩系スイーツ」
この手法は特に、成熟市場で「もう新しいものは生まれない」と思われている分野で効果を発揮します。
4. ユーザーペルソナ深掘り法:顧客を徹底的に理解する
ユーザーペルソナ深掘り法は、ターゲットとなる顧客像を具体的かつ詳細に設定し、その人物の生活や価値観、課題を深く理解することでニーズに合った商品を企画する手法です。
単なる年齢や性別だけでなく、ライフスタイル、価値観、悩み、日常の行動パターンまで詳細に設定します。

例えば、「健康に気を使いながらも忙しく、手軽に栄養補給したい30代共働き女性」というペルソナを設定したとします。彼女の朝の準備時間、通勤方法、仕事内容、帰宅後の過ごし方、休日の趣味、情報収集方法などを細かく想定します。
そこから見えてきた「朝の準備時間が限られている」「通勤中に食べられるものが欲しい」「見た目にもこだわりたい」といった具体的なニーズに応える商品として、「片手で食べられる、見た目も美しい栄養バランス朝食バー」を企画。パッケージも通勤バッグに入れやすいスリムな形状にするなど、ペルソナの生活に寄り添った商品設計が可能になります。
ユーザーペルソナを作る際は、実際のユーザーインタビューやアンケート調査のデータを基にすると、より現実に即したものになります。
効果的なペルソナ設定のポイント
- 名前や年齢、職業などの基本情報を設定
- 1日のタイムスケジュールを時間単位で想定
- 価値観や大切にしていることを明確化
- 情報収集の方法や影響を受けるメディアを特定
- 食に関する悩みや理想を具体化
この手法は、ターゲットが明確な商品開発において特に効果的です。
5. トレンドハイブリッド法:複数トレンドの掛け合わせ
トレンドハイブリッド法は、複数の市場トレンドを組み合わせることで、新しい価値を持つ商品を企画する手法です。
単一のトレンドに乗るだけでなく、異なる分野のトレンドを掛け合わせることで、より独自性の高い商品企画が可能になります。
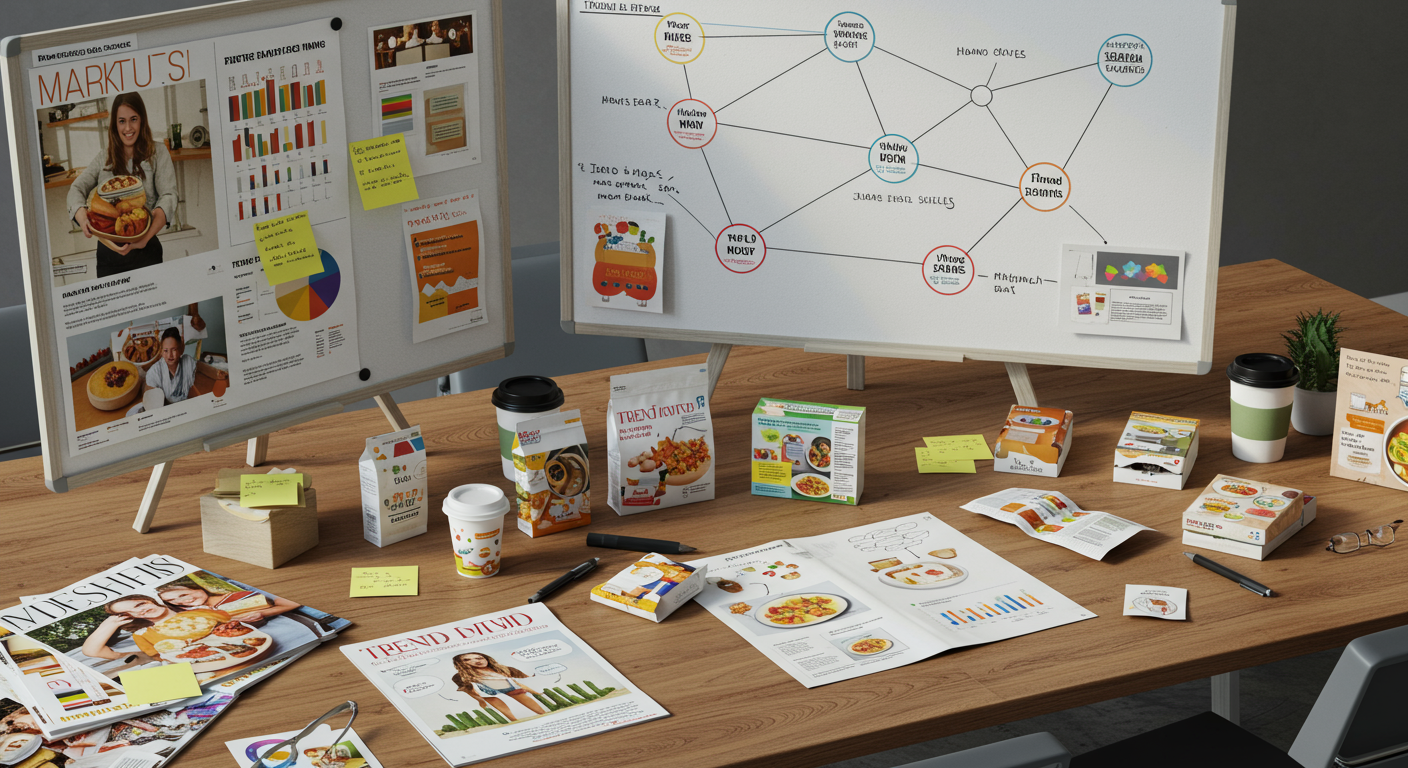
例えば、「健康志向」と「時短ニーズ」と「サステナビリティ」という3つのトレンドを掛け合わせた「食べられる容器に入った完全栄養食」という商品企画が生まれました。食品自体の栄養価の高さだけでなく、容器まで食べられることで廃棄物を出さない環境配慮と、洗い物の手間が省ける時短の両方を実現しています。
別の例では、「発酵食品ブーム」と「ご当地食材人気」と「おうち時間充実」を掛け合わせた「各地の伝統発酵食品を自宅で手軽に作れるキット」が話題になりました。トレンドハイブリッド法を実践するには、常に様々な分野のトレンド情報をアンテナを張って収集することが大切です。
トレンドハイブリッド法の実践ステップ
- 現在注目されている食品トレンドをリストアップ
- 食品以外の分野(テクノロジー、ライフスタイル、環境など)のトレンドも収集
- 2〜3のトレンドを選び、掛け合わせた場合のアイデアを発想
- そのアイデアが解決する課題や提供する新しい価値を明確化
この手法は、「差別化」と「市場適合性」の両立を図りたい場合に特に有効です。
6. 原材料再発見法:素材の新たな可能性を探る
原材料再発見法は、既存の食材や原料に新たな視点で光を当て、これまでにない活用方法を見出す手法です。
従来とは異なる調理法や加工技術を適用したり、意外な組み合わせを試したりすることで、素材の持つ可能性を最大限に引き出します。

例えば、これまで主に和食に使われていた「米麹」を洋菓子の材料として活用し、独特の風味と自然な甘みを活かした新しいスイーツを開発。従来の洋菓子にはない、日本人の味覚に合った商品として差別化に成功した事例があります。
また、廃棄されることの多かった野菜の皮や茎を乾燥・粉末化し、栄養価の高い調味料として商品化。食品ロス削減という社会的価値と、新しい食体験の提供を両立させた例もあります。原材料再発見法を実践するには、既存の原材料に対する固定観念を取り払い、「もし違う使い方をしたら?」と常に問いかける姿勢が重要です。
原材料再発見のアプローチ
- 従来とは異なる調理法・加工法の適用(例:蒸す→燻製にする)
- 異なる食文化の調理技術の導入(例:日本の食材×中東の調理法)
- 未利用部位の活用方法の模索(例:魚の骨→出汁パウダー)
- 複数素材の意外な組み合わせ実験(例:抹茶×オリーブオイル)
この手法は、地域の特産品を活かした商品開発や、サステナブルな食品開発において特に効果的です。
7. 顧客共創法:ユーザーと一緒に作り上げる
顧客共創法は、商品開発のプロセスに実際のユーザーを巻き込み、彼らの声やアイデアを直接取り入れながら商品を企画する手法です。ユーザーのニーズを推測するのではなく、開発の初期段階から協働することで、真に求められる商品を生み出します。

例えば、特定の健康課題を持つ消費者グループと共同で、彼らの日常的な悩みや理想の食生活についてワークショップを実施。そこから生まれたアイデアを専門家が形にし、再度フィードバックをもらいながら改良を重ねる過程で、市販の健康食品にはない実用性と満足度の高い商品が誕生しました。
別の例では、SNSで人気のフードインフルエンサーとコラボレーションし、そのフォロワーの意見も取り入れながら商品開発を進めることで、発売前から高い認知と期待を獲得した事例もあります。
顧客共創法の最大の利点は、商品発売前に市場の反応を確認できること、そして開発に参加したユーザーが熱心な支持者となり口コミを広げてくれることです。
顧客共創法の実践ステップ
- ターゲットとなる顧客グループの選定と招集
- アイデア出しワークショップの実施
- プロトタイプ作成と顧客フィードバックの収集
- 改良を重ねた最終製品の開発
- 開発ストーリーを含めたマーケティング展開
この手法は、ニッチ市場向けの商品開発や、顧客ロイヤルティを重視するブランド構築において特に効果的です。
まとめ:差別化されたOEM商品企画のために
食品OEMで真に差別化された商品を企画するためには、従来の発想を超えた創造的なアプローチが必要です。本記事で紹介した7つの手法は、それぞれ異なる角度からアイデア創出をサポートします。
これらの手法は単独でも効果的ですが、複数の手法を組み合わせることで、さらに独創的な商品企画が可能になります。例えば、「市場ギャップ分析」で見つけたニーズに対して「逆転発想法」を適用し、さらに「顧客共創法」でブラッシュアップするといった組み合わせです。
最後に大切なのは、これらの手法を形式的に実施するのではなく、常に「なぜこの商品が必要とされるのか」「誰のどんな課題を解決するのか」という本質的な問いに立ち返ることです。
食品OEMの世界で真に差別化された商品を生み出すために、ぜひこれらの手法を実践してみてください。あなたのビジネスに新たな可能性をもたらすことでしょう。
食品OEMのマッチングや商品開発についてさらに詳しく知りたい方は、食品OEMの窓口にぜひご相談ください。あなたのアイデアを形にするための最適なパートナーをご紹介します。